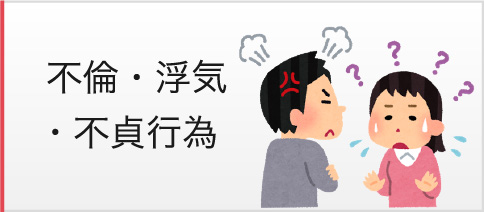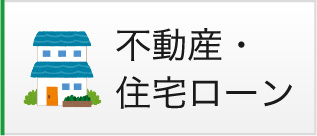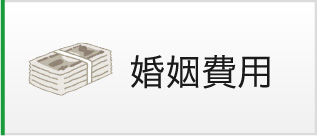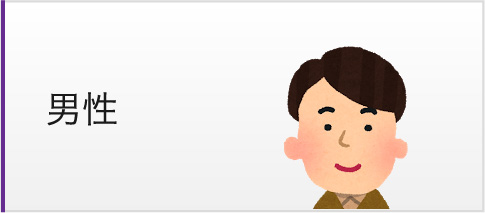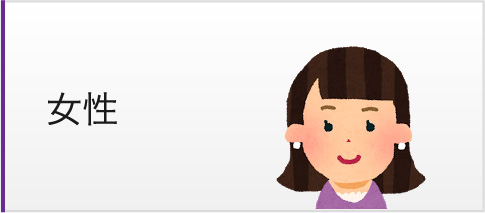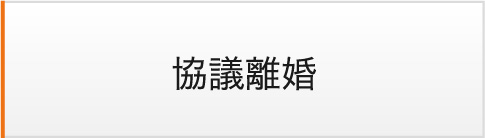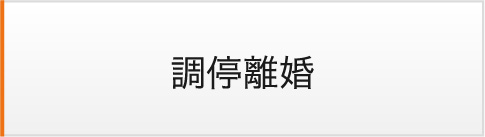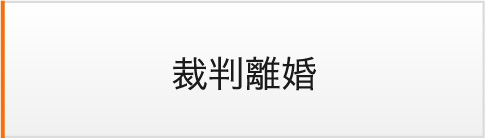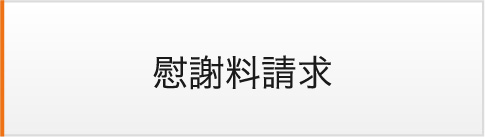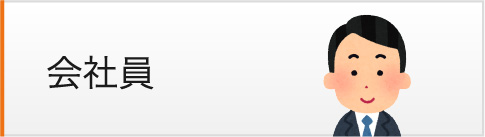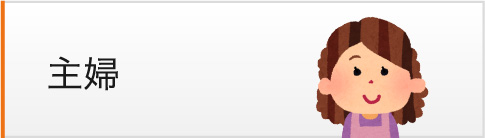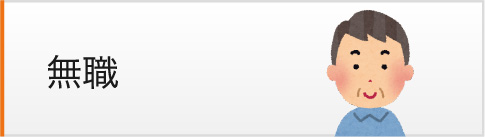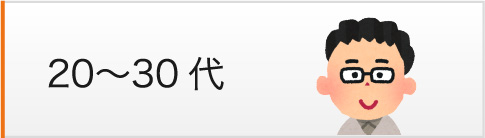離婚のトラブル解決事例
【面会交流・養育費(婚姻費用)】別居親との接触を拒否していた思春期の子との、1か月あたり複数回の面会交流が実現した事例
- 依頼者:男性(40代)公務員
- 相手方:女性(40代)パート
- 子ども:2人
事案内容(相談までの背景)
妻が子どもを連れて家を出て行き、妻から婚姻費用請求調停が申し立てられ、夫は夫婦関係調整調停(円満調整)及び子らとの面会交流を申し立てていました。
当事務所の活動結果(受任から解決まで)
2人の子ども(15歳、8歳)が精神的に不安定で、直ちに面会交流を実施することが望ましくない状況であったため、調査官調査及び試行的面会交流を経た上で、面会交流のルールを条項化しました。特に、15歳の子は、思春期にあり、当初、父親(依頼者)との面会を拒否する態度を取っていましたが、父親が子に対する思いを手紙で伝えるなどして父子関係の改善を図り、最終的には父子で自由に連絡を取り合い、宿泊も含む月複数回の面会交流を実現することができました。
なお、子どもの状況を考慮し、夫婦双方が別居しつつ婚姻関係を継続することを望んだため、夫婦関係調整調停は取下げました。
また、婚姻費用の調停が一旦成立した後、妻(相手方)より、算定表の改定(令和元年12月)等を理由に婚姻費用増額請求調停が申し立てられましたが、双方の現状の収入に照らし、現状維持が相当である旨指摘したところ、同調停は取下げられました。
解決のポイント(所感)

精神的な問題を抱えた子どもとの面会交流を実現することは、繊細で、難しい問題です。調査官調査を実施したり、相手方(同居親)の協力を得るなどして、子の別居親に対する思いを知り、親子の行き違いを埋める努力を行い、時間をかけて信頼関係を築いていく必要があります。
調停成立の際には、このように時間をかけて築いてきた親子の信頼関係を崩さないよう、また、相手方(同居親)の協力を得られるよう、面会交流の実現を確保しつつも、相手方(同居親)及び子にとってプレッシャーとならないよう、バランスのとれたルールを定めることが大切です。
「養育費(婚姻費用) , 面会交流」カテゴリーの他の事例
- 【財産分与・養育費(婚姻費用)・不倫】調停を自分で行っていたが、弁護士に依頼して早期に離婚が成立した件
- 【財産分与・慰謝料・面会交流・養育費(婚姻費用)】高額所得者の婚姻費用・養育費を比較的低額におさえた事例
- 【財産分与・養育費(婚姻費用)】受任から僅か1ヶ月半で離婚合意が成立し、特に夫側から妻側に財産分与金を支払わずに済んだ事例
- 【慰謝料・親権者指定・婚姻費用・不倫】不貞をした夫に長期間の生活補償を約束して離婚調停を成立させた事例
- 【婚姻費用】いったん調停で取り決めた婚姻費用について、子供の監護者が変更したことにより、3分の2に減額された事例
- 【財産分与・養育費(婚姻費用)】長期間夫から婚姻費用(生活費)を払ってもらっていなかったが、離婚にあたって、財産分与として、未払婚姻費用に相当する金員を回収できた事例
- 【養育費(婚姻費用)・財産分与・慰謝料・面会交流】話し合いにより、相手方の請求額を大幅に減額させて、離婚を成立させることができた事例
- 【財産分与・面会交流・養育費(婚姻費用)】財産分与・養育費・面会交流と争いがたくさんある事例について、なんとか調停で満足のいく解決ができた事例
- 【財産分与・養育費(婚姻費用)】不動産を早期に売却し、また別居直前の使途不明金を財産分与額に組み入れて、財産分与の問題を解決し、養育費についても15歳以降の変更を予め合意して離婚が成立した事例
- 【面会交流・親権】父親側にいた子供の監護権を母親側に認めるように請求がありましたが、父親側で監護することで解決した事例