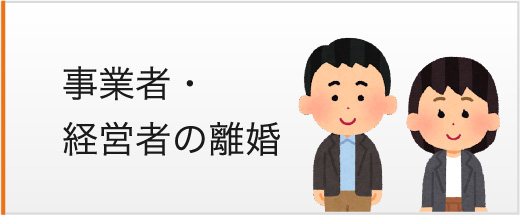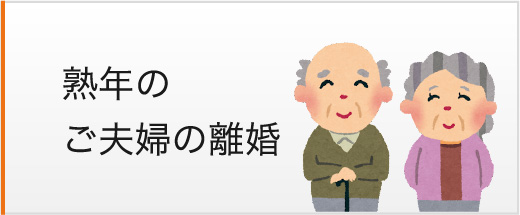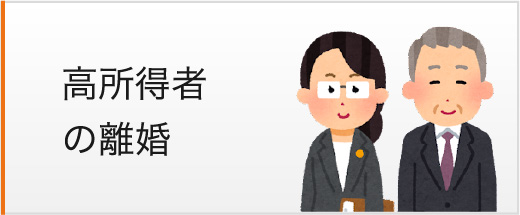医師の離婚
医師の離婚
夫婦のどちらか、あるいは双方が医師の場合、離婚にあたって考慮しなければならない特有の問題があります。
医師は、一般に年収が高く、財産の種類も多様且つ多額であるため、慰謝料や財産分与、養育費などが高額化・複雑化して紛争となりやすい傾向があります。

他の職業との違い
(1)財産分与
①財産分与の割合
一般的な夫婦の離婚だと、財産分与の割合は基本的には2分の1ですが、夫婦のどちらかが医師である場合は、その割合が修正されることがあります。
福岡高裁昭和44年12月24日判決では、「夫が医者として病院を開業し、年収が1億円を超え、1億円を超える資産を保有している事案で、2分の1を基準とすることは妥当性を欠く」として、妻に2000万円の財産分与しか認めませんでした。ただ、この裁判例は古いものですので、現在も妥当するかどうかは分からず、よく争いになります。
②対象財産について
医師には退職金がないと誤解されていらっしゃる方がおられるかもしれません。しかしながら、勤務医の場合でも勤務先と勤務年数によっては、退職金が出るところもあるようです。さらに、医師が医療法人の理事長等の役員である場合、退職金に関する保険をかけていることもあり、これが財産分与の対象となる余地があります。
なお、医療法人の財産は、あくまで法人の財産ではあり、財産分与の対象にはなりませんが、持分の払戻が可能な場合は財産分与の対象となり得ますし、法人への貸付等がある場合もあり、財産関係をよく調査する必要があります。
(2)婚姻費用・養育費
医師の場合、収入がとても高額になるため、裁判所が用意している算定表の年収を軽々と超えてしまうケースがあります(年収2000万円以上)。
そのため、複雑な計算で婚姻費用や養育費を算定する必要が生じます。
なお、高額所得者の婚姻費用・養育費算定については、種々の見解があるため、大変難しいです。
また、子女を医師にしたいと希望される場合は、養育費の期間についても紛争が生じやすいです。
(3)その他
開業医の方のなかには、従業員として配偶者を雇用されている場合もあります。
離婚を理由に解雇することは困難ですが、労働の実態が無い場合は、雇用関係を否定することができるかもしれません。